


|


「日本の食文化」
朴 恵蘭(韓国)
日本にはじめて来たときに、友人が連れて行ってくれたところが、カレーうどん屋であった。どちらかというと、麺類が好きでない私は、あまり乗り気でもなかったが、母国韓国にはない食べ物なので、仕方なく付いていった。ともかくも、食べ物だからと思って我慢をしても食べようと思って、一口口にした。美味しかったのである。カレーうどんを始めとして、後日、ヤキソバも美味しいかもしれないと思って、ヤキソバも食べて見た。
韓国では、全く味わったことのない味が、身近に存在しているし、何よりも美味しかった。そのことが、調理の学習研究を進めて行きたいと思う、大きな一歩になった。
もっとも失敗があった。カレーうどんは、すぐに作れないまでも、ヤキソバならば、家庭で作れると思って、ある日ヤキソバを作って見た。私の家族は、もちろん韓国人だが、あまり、美味しいとは言ってくれず、むしろ評判が悪かったために、がっかりした。いろいろ反省して見ると、どうも原因はソースにあったようである。評判の悪さが、研究心を駆り立ててくれた。調理の研究ができる大学の受験を目指して、日本語学校に通っていたときのことであった。
韓国と日本とは、近くて遠い国と言われるように、地理的には緯度も経度も近いけれども、お互いが似ていることもあって、意識的には、極めて競合しやすい民族同士であるように思う。それだけに、お互いにわかっているつもりで、わかっていないことが多々ある。その具体的な例が食文化であろう。お箸を使うし、お雑煮はあるし、巻きずしもうどんもあるしということが、共通性の大きな原因であろう。しかし、立ち入って一つ一つの事象を見てゆくと、両国の食文化の差には、食哲学とも呼んでよいような、奥深い食文化に対する考え方の差があると思う。
第一に、食卓に載る「お箸」と「お匙」の問題がある。細かいことは抜きにしても、韓国では、食卓にお箸とお匙とは欠かせない。今でこそ、お箸で御飯を食べたからといって、親から注意されるようなことはないとしても、元来御飯はお匙で食べるものと決まっていた。お箸で食べるのは無作法として叱られたものである。ましてや、御飯のお茶碗を持って食べるなどということは、お箸で御飯を食べる以上に無作法なことであった。韓国で、お茶碗を持って食べる食事作法が嫌われたのは、貧しい乞食の貰い歩きに原因があるかもしれないし、日本でお茶碗を持って食べなければ、前かがみになってしまって、まるで犬が物を食べるような食べ方として嫌われたことも、後に知ったことであった。和食で、お匙が使われなかったのは、歴史的なことも関係あったかもしれないが、我が国韓国では、歴史的な遺品にも、お匙が残っており、その歴史が古いことが理解できる。
第二に、食生活における、礼節の問題がある。先に述べた事柄も、礼節と関係が深いと思う。韓国では、とりわけ礼節の基本が食文化にある。現在は、貴族階級であった両班(ヤンバン)の文化そのものを継承することはない。しかし、両班が築いてきた礼節の考え方は、儒教文化としても、深く国民に浸透している。家父長制度が徹底していた時代には、家族全員が揃って食事をすることがなかったのだが、近代化が進み、家族関係に民主的な人間関係が確立されてきた。今日では、古い時代の美徳が美徳でなくなってきたのである。しかしながら、韓国では食事の時に、家父長である人が手を付け始めなければ、絶対に食事を始めてはならない鉄則が、はっきり守られている。会食などのときでも同様で、教養の度合いが食事作法に現れるほどに、食事の礼節については、厳しい習慣を守っている。
一方、日本での礼儀作法では、「いただきます」「ごちそうさまでした」という、食前食後の挨拶が、本当に綺麗にされている。大学の食堂でも、時に、学生が食膳に向かって合掌してから食事を始める姿を見かけることがある。たしかに美しい。西洋人も、食前に「主の祈り」をする光景を目撃するが、西洋の習慣として、食後に感謝の気持ちを籠めた礼節の表現があるのかどうかを知らない。韓国にも、「おかずが少なくて失礼だが」と言った挨拶に対して「戴きます」とか、「本当に美味しく戴きました」という表現は、日常的に使用しているが、日本人ほど徹底した挨拶には、なっていない。食事に対する感謝の念の教育が深く浸透しているためであろう。
私は、前にも述べたように、料理を勉学している一人の学生である。それだけに食生活に対する思いは、他の留学生よりも敏感かも知れない。私が母国を離れるときに、それなりに料理にも自信を持っていたし、技術的にも一般の水準よりも高いレベルにあったと思っている。しかしながら、微妙な味付けの問題については、本当に苦しい思いを持ち続けている。日本の料理の特性は、韓国との視点と違って、間違いなく季節感を重視している。母国韓国よりも、日本は春秋が少しずつ長い。日本は、穏やかな気候の期間がとても快適である。そのせいか、春秋の期間の旬の食材には、素晴しいものが多い。例えば、春のタケノコ、鯛、秋のキノコ、サンマには、その料理法の多彩さと共に、驚異的なほどの豊かさがある。また、盛り付けにおける、中間色的な色彩感、盛り付けに調和する、見事な器ものの贅沢さは、まるで美しい映画の一コマを見る思いである。それが、普通の家庭料理の中にまで、持ち込まれているのが素晴しい。母国韓国の宮廷料理においても、季節感が尊ばれ、器ものに工夫が凝らされ、色彩は、赤、青、黄、黒、白の五色を基本とする、色彩美が強調される。また、味付けでも、甘さ、塩辛さ、辛さ、苦さ、すっぱさが基本であるが、最近では、大切な味として「旨み」が強調されている。日本との視点の差は存在するが、独自の伝統的な料理の世界がある。しかし、最初に触れたように、季節感だけは、日本独自の発達をしてきた世界であるようだ。
日本では、韓流ブームが続いている。我が国では日本文化の開放が続いている。重苦しい歴史問題を持つ両国にとっては嬉しいことである。「チャングムの誓い」(原題「大長今」)は、母国でも好評であったが、日本でも評判がよいことを知ってとても嬉しい。とりわけ、料理に関する映像や、宮廷の調理法や、数々の料理の知識は、専門の立場にある人からも大変参考になったということを聞くことが多い。たとえば、黄砂の話である。宮廷での料理が腐りやすい中で、主人公である幼いチャングムの厨房だけは食べ物が腐らない。不思議に思った女官(尚宮)たちが、原因を調べて見ると、チャングムだけが水を煮沸して使っているという。聴けば、かつて宮廷で料理人であった母親から水で煮沸することを教わったという。幼い子供のときのチャングムに伝えられていた母親の知恵の深さと、ドラマであるとはいえ、科学的でなかった昔、健康や安全に気をつけていた、伝統的な母親の知識を見ることが出来て、深く感動した。
「チャングムの誓い」を通じて、料理は心であると教えられている。また真心がなければうわべだけでの小手先の料理では本当の味は出ないと、何度も痛感した。時間をかけた「陰干し」が大切であるとか、三十種類以上の医薬水と呼ばれる水の微妙な味とか、次第に知識を得てきた。また、全ての料理の基本である水については、韓国では大変大切にしている。極端に言えば、水の種類だけでなく、水の飲み方にまで注意を払うのである。例えば、のどが渇いている人に水を差し上げるときに、器の中に柳の葉などを、目立つように入れて、水を飲む人が慌てて水を飲まないような心配りを欠かしてはならないといったことを、子供のときから母親や昔話を通じて学んでゆくのである。自信をつけてきた私は、再びヤキソバを家族に作って見ることにした。時間をかけて、とリわけソースに工夫を加えて、自分では満足したつもりで、試食をしてもらうと、たしかに前より美味しくなった。しかし、どうも味がもう一つだという。私は悩んでしまった。問題はソースだ、ソースを工夫することが大変なのだと自覚してきたのである。
そんなときに、バイオリン製作者として世界的に有名な陳昌鉉先生のお話を知る機会があった。先生は『海峡を渡るバイオリン』の著者としても良く知られた韓国の方である。先生は、人間の耳は20Hzから30kHzまでしか聞こえないものである。しかし、自然の美しい音は、その音域を越えて超低音、超高音となる超音波を感じるはずだ。また、440Hzのラの音の、倍音880Hz、その上の1200Hzさらに5倍10倍、100倍、1万倍の振動が存在する。その無限の振動が名器のバイオリンにあると述べられて、「音というのは料理みたいに隠し味がある」と述べられていた。人の心には、確かに描ききれない広がりがある。チャングムの場合も、味覚を失っていたとき、「味を描きなさい」という指導を受けているのを知って、料理の道は、深いものだと思ったけれども、陳昌鉉先生の一言は、私に大きな衝撃を与えた。音楽の世界から教えてもらった「隠し味」である。
隠し味については、チャングムでも出てくるし、私自身も、日本語の隠し味の表現は知らなかったが、たしかに隠し味が必要なことをよく理解していたつもりであった。チャングムでは、牛肉の味を引き立てるために牛乳を使うとか、それとわからずに味付けするときに香料を使うのである。しかし、大学の先生から和食を教えていただいたときに、隠し味が必要であることを、本当に何度も何度も教わって、自分でそれなりに分っていたつもりであった。でも違う。陳昌鉉先生のお言葉で、本当に見えないはずのもの、聞こえないはずの音、味わえないはずの味覚に到達してゆくことが、本当の隠し味であるということを教えていただいたのである。味がよくなるだけではない。食材を引き立てるだけではない。真心を籠めて料理を作るだけではない。それ以上に深い、食べていただく方の心に響く音を伝えられるような料理人としての自覚を持って一日一日を努力してゆきたいと思う。
もし、私が料理人として大成することがあったしたら、何よりも陳昌鉉先生のお言葉が私を勇気付け、私を導いてくださったということを、心を籠めて御礼を申し上げるつもりである。そして、自分の道を切り開こうとして悩んでいた私には、今新しい出発ができる自分を発見できた気がしてとても嬉しい気分である。「私が見た日本」の表題で応募する機会がなければ、新しい日本も私も発見できなかったかもしれない。心から感謝したい。
|
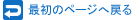 |
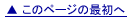 |
|


