


|


「私の見た日本人たち」
車 小平 (中国)
私が日本人の人と人との関わり方について初めて学んだのは日本に来てからではなく、すでに20年前にイラクのファルージャにいた時でした。日本人にとってイラクは歴史上でも関係の薄い遠い国でした。バグダッド近郊の小さな町のファルージャは日本で販売されている地図には載っていないし、この地を知っている日本人は極めて少なかったはずです。湾岸戦争の時、イラクは侵略者として攻撃されたので、以来、日本人の茶の間で話題になったことがありますが、激しく爆破されたファルージャはそれでも日本の新聞に大きく登場したことがありませんでした。しかし、最近になって日本人の人質事件が発生して以来、ファルージャというところは突然日本中で注目されるようになり、武装グループに脅された人質の映像を見て、日本人が恐ろしい武装グループに殺されたらどうしようと、話題になっていました。
しかし、私は一人日本で日本の人質がファルージャの人に殺されることはないだろうと初めから信じていたのです。では、私はどうして「ファルージャでは日本人の人質が殺されることはない」という確信を持つにいたったのでしょうか。その答えが、これからお話する約20年前の私の体験なのです。話は1983年に遡りますが、当時28歳だった私は文化大革命時の厳しい労働にも耐え、外国語大学の日本語科を卒業して、通訳として初めて国の命令で海外に派遣されました。その任地がファルージャだったのです。
当時、日本のF社がイラクの高速道路工事を請け負い、中国、フィリピン、インド、タイ、バングラディシュ、スリランカなどの国から作業員の提供を受け、高速道路建設のための‘多国籍軍’が編成されたのです。‘多国籍軍’の仕事の振り分けは、フィリピンは舗装、タイ、バングラディシュ、スリランカなどは盛土、中国は橋梁となっていました。F社のイラク高速道路作業所はベースキャンプをラマディーの郊外に設けていましたが、中国の橋梁キャンプは丁度ファルージャの郊外に位置していたので、毎日ファルージャを通って、現場へ通っていました。
ファルージャはユーフラテス川を臨む小さい町で、イラクのアンバル州にあり 、バグダッドから西に約60キロ、バグダッドとヨルダンを結ぶ要路に位置し、人口は約30万人、潅漑設備を用いた農業が産業の中心でした。私が働いていた数年間、犯罪事件は一度も聞いたことがない平和なところで、日曜日は時々ファルージャへショッピングに行ったりしたのですが、道の両側に金のアクセサリーの店がずらりと立ち並ぶ、物資豊富で市場が繁栄している町でした。ちょこで、酒ではなくコーヒーを飲みながらアラビアの音楽を楽しむイラク人が町の至る所に溢れ、椰子に似た樹形のナツメヤシの森が至る所に茂っていていました。その実は新鮮な柿の味に近いのですが、成熟すると、糖分が多く砂糖漬けのようで、イラクの人々は一年中働かなくてもナツメヤシだけで腹いっぱいにすることができました。しかし、殺生が禁じられているので、蝿も沢山繁殖し、五月に入ると食堂の天井にはいつも隙間なくびっしりと蝿がくっつき、寝る時も数十匹が顔に集まるので、アラビア人がいつも顔に被っている布が非常に役立ちました。「五月蝿い」という言葉の発明者もたぶんこれと同じような体験をしたことがあるのだろうと思います。
砂漠というと、よく不毛地帯と同じようなものが想像されるようですが、イラクの砂漠はほとんど未開発の肥沃な土地です。ファルージャはアルカリ性の土壌なので、野菜にも果物にも適し、仕事の余暇に野菜を植えれば、食べきれないほどの収穫がありました。夏になると、美味しいスイカが沢山出回るばかりでなく、とても安く、私たちは猫車を押して買いに行ったものです。
一方、自然環境のきわめて厳しい面もあります。一年中、ほとんど夏で、日本の一番暑いところよりもはるかに暑いのです。4月になると、砂嵐が多発します。突然、天空から筵を巻くようにザワッーと襲い掛かってきて、逃げようにも逃げられない砂嵐の恐怖感は津波と同じです。砂嵐が襲ってきたら、私たちは急いで橋桁の下に潜って避難しますが、2、3時間後、砂津波の嵐が通り過ぎると、みんな泥人形になってしまいました。それにもかかわらず、日本の技術者を始めとした‘多国籍軍’は見渡す限り砂漠という土地で‘現代のシルクロード’を建設しようという情熱に燃え、元気はつらつとして大自然に挑み、昼夜分かたず灼熱の砂漠と戦っていました。
暑さから身を守るために、仕事中は製鉄工場の作業員のように、頭を完全に覆い、分厚い袷の作業服を着、厚底の革靴を履き、現場へ行くのです。土木の作業は力仕事で、その高温ですから本国の仕事より数倍も辛いものでした。イラクでは汗をかく感じがせず、しばらく働くと、顔に白い塩粒が撒きつけられた様で、服にも塩水の痕がシマウマのようについていました。橋梁のコンクリート打設が始まる頃には、仕事の辛さはいわんや連日12時間以上も烈日に曝され煉獄の苦しみを嘗め、夜も作業所で12時まで働くのが普通でした。日本のスタッフと比べて割に楽な仕事の私でも10日間ベッドにつけませんでした。このような厳しい条件下でも、手をぬくことなく橋梁建設は進められて行きました。私は赴任前に本国で土木工事に関する専門用語を習うなどの期間はありましたが、それだけでは足りず、現地で日本のスタッフたちからの厳しくも親切な指導が不可欠でした。その真摯な態度に感化され、私も深夜でも電気がついているトイレなどで勉強し要求に応える努力をしたものです。
厳しい自然環境、仕事の重責、我々への指導などで日本人スタッフの毎日は並み大抵のものではなかったはずです。たまに催されたカラオケ大会では家族への思いを託した歌が歌われ、祖国を離れて仕事をする人々の苦悩も感じました。
当時のファルージャは『アラビアン・ナイト』に出てくるような彫りが深い美男美女ばかりの異郷で、日本人スタッフは高校生や時おり通る羊の群れにも車を止め、礼儀正しく道を譲っていたのです。ファルージャの住民はいつも親指を立てそれに応え称賛の意も表していました。地元の人々との付き合いもお互いに何の疎外感もなく、週末はよく現地人の家にも招待され、らくだの焼肉をご馳走してもらっていました。また、日本の祭りを催し、食材を提供し、工事現場で働く人のために来ている各国の調理師に中華料理、インド料理、タイ料理、フィリピン料理を作ってもらい、ファルージャの住民を招待することもありました。ファルージャの人々が大喜びで子供連れで集まってきた時は、キャンプがまるでにぎやかな夜の市のようになりました。それだけではなく、時々地元の青年たちとサッカーの親善試合を行いました。が、向こうは練習に練習を重ねた15歳前後の若者ばかりで、対する日本チームには非常に不器用な白髪交じりの課長や部長たちで無理して走っているという状態。その様子が滑稽に見えて、観衆たちは大笑いしましたが、それに対して私は深い敬服の意を抱いていました。その中年太りの課長や部長たちはお前たちのために苦労しているのだぞ、お前たちを救ってやっているのだぞという気持ちは毛頭なく、きつい仕事をする傍ら、地元の人々と仲良くしたくてサッカーなどを付き合っていたからです。
ファルージャで橋梁工事をしていた時は、ちょうどイラン・イラク戦争の最中で、フセイン統治の全盛期でもありました。フセインの塑像が至る所に立てられ、外資企業もフセインの肖像画を掲げるのが義務付けられていたようで、私の机の後ろにも美男子のフセインの絵が掛けてありました。個人崇拝は中国の文化大革命時代にもありましたが、将軍服を着たフセインはカッコよくても、写真がいくらきれいに撮影されていても、南部のバスラ地方で激しい戦闘を起こし、青年たちの命を奪っていたのです。私たちが現場で働いていた時も、時々、青い空にイラクとイランの戦闘機がぐるぐる回って、空中戦を交え、耳を聾するばかりにとどろくほどの砲声が聞こえていました。可笑しいのは地上にいる人々が誰も避難などしないことでした。当時のイラク人の認識では戦争は軍人の仕事で、戦争を見る心境はイラクとイランとのサッカー試合をみているのとあまり変らないようでした。私達が知っている第二次大戦時や今のイラクのように普通の人々までは戦争に巻き込まれていなかったのです。
イラクでは日本は高速道路だけでなく、バクダッドの都市下水、病院、ダムなど、沢山のプロジェクトを行いました。私が日本の技術者と一緒に働いたのは1983年から1986年まででしたが、日本のスタッフたちは十数年間もイラク各地で汗を流し、苦労を味わっていたのです。その時のすべての善行は間違いなくファルージャを初めイラクに住む人々の心に焼き付いているものと確信しています。そして、私も毎日日本のスタッフたちと苦楽を共にして、共に働き、戦場で死に際に結びついたような固い友情は、それから20年ほど経っても変わることなく 、今でも連絡を取り合い人生の旅路でお互いに励ましあい、助け合ってきています。
時の経つのは本当に矢のごとくで、若造の私も50歳になり、両鬢は白髪混じりになってしまいましたが、ファルージャの日本のスタッフから学んだ向上心が依然燃え続けています。今年2月から早稲田大学で毎日10代、20代の若者とともに授業を受け、勉強すればするほど知識不足を感じ、もう一度ファルージャにいた時と同じ20代に戻りたくてたまりません。かつてファルージャで共に働いた元気いっぱいの日本の旧友たちはそろそろ還暦を迎え、近いうちに全員定年になるのですが、今度は再就職難や年金問題などに悩まされているようです。定年後の生活はどうなるのでしょうか。豊かな土地に私達が造ったファルージャ近くの数十基の橋は湾岸戦争の時、全て爆撃で崩れてしまったそうです。さらに、今度の戦いでファルージャはすでに地獄のようになってしまったようです。ファルージャで悪戦苦闘していた民間交流の功績も無言のまま埋もれてしまうのでしょうか。
政府のことをいろいろ言うのではなく、自分の力でできる何かをする日本人の姿勢はイラクで私は20年前にも見ていました。そして、20年前とよく似た姿を今年も目にすることができました。昨年11月、ファルージャの戦闘に巻き込まれ、左目を負傷した10歳のモハマド・ハイサム・サレハ君の支援のことです。サレハ君は殺害されたフリー・ジャーナリスト橋田信介氏の遺志をついだ人々の手で静岡県沼津市の病院で治療を受けました。天真爛漫な顔、あどけないつぶらな瞳、可愛い手を振って日本の皆さんに挨拶をしている姿が日本の新聞に大きく載りました。日本全国から届いた彼の治療費や支援金の総額は1700万円にも上ったという報道もありました。そして、包帯姿のサレハ君は亡くなった恩人橋田氏の奥さんに対面した際、自分の目が日本の医者に救われたので、医学のありがたさに感動し、「将来お医者さんになりたい。特に眼科医がいい」と笑顔で話しましたが、テレビの前で、それを見た人々がどれほど感動し、涙を流したか、サレハ君もおそらく知らないでしょう。治療を受けて帰途につくサレハ君は橋田氏の妻の幸子さんに抱きしめられると、照れたような笑みを浮かべ、「ほんとうに、ありがとうございました」と、つかえながらも日本語でお礼を言い、 幸子さんはサレハ君について「信介が言っていた通り、賢そうでかわいい子。これからはとにかく生き延びてほしい。亡くなった2人の目の代わりに世界やイラクを見て、イラクの役に立つ人になってくれたらうれしい」と語ったとのこと。ごく普通の言葉で、何の美辞もありませんが、その中の『とにかく生き延びてほしい』という言葉には平和な環境に暮らしている人にとってはまったく無意味なものかもしれませんが、まだ戦乱の渦中にあるファルージャに帰るサレハ君には、どれほど貴い言葉でしょうか。同じころのある日本人の報告には「現在ファルージャの状況は絶望的であり、手足が吹き飛ばされた子どもをファルージャから運び出しているというまったく生き地獄のようになってしまった」とありました。罪のない人の命まで危ぶまれるこの世の地獄に帰っていくサレハ君の後ろ姿を見つめていた橋田夫人の顔には果てしない憂うつと大きな不安が浮かんでいるようでした。そのときの顔を見て、いろいろな思いが心の中をよぎりました。戦場に向かう息子を見送る母親の顔や、文化大革命中、初めて家を出、遠隔地へ危険な鉄道工事の仕事に向かう17歳の私を見送ってくれた私の母の顔も思い出されました。当時、中学校を卒業したばかりの私も世間知らずでうきうきしてトラックの荷台に上りましたが、私の姿を見つめている母は涙を忍んで、無言のまま手をゆっくり振りながら、さようならをするシーンは今でも忘れることができません。幸子さんの姿が戦場に息子を送る母親や私の母に重なるのは、実の親のような無償の愛が存在するからでしょう。
私はふるさとの四川省で、微力ながら両国の友好のために力を捧げる気持ちを常に持っています。中日両国もかつて戦争をした時がありました。祖父も父も昔八路軍の兵士で、日本軍と激しく戦いを交えたことがありました。しかし、そのような中でも日本人の子供を助けたことがあるという話も聞かされました。善人も戦争中は悪魔に化けてしまうから戦争は絶対嫌なのですが、平和な時代はもとより、戦時中であっても人々の心はつながり合うのです。そして、それを実行に移しやすいのは私たち民間人であることを忘れたくありません。
私の名前には「平」という字がついていますが、祖父と父は戦争を経験したことから、子々孫々が二の舞を踏まないようにと切願してつけた名前です。私は戦争を経験したことはありませんが、祖父と父から平和の尊さを教えられ、日本の平和憲法をとてもすばらしいと思っています。
若い時代の記憶はなかなか忘れがたいようで、ファルージャで初めて見た“日本”はただ瞬間的に目だけで見たものではなく、三年間、栄辱を共にして異国で働いていたF社のスタッフから肌で感じたものです。その後何回か訪日しましたが、F社を通して見た“日本”についての印象ほど深いものはないのです。
21世紀は「協働の時代」と言われていますが、50年以上も平和な社会で生活して来た日本人は自分達の方法で、人と人とのつながりを何よりも大切にしてきたわけですが、そのような人との関わり方が全世界に広がっていくことを私は切に希望しています。
|
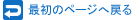 |
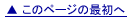 |
|


